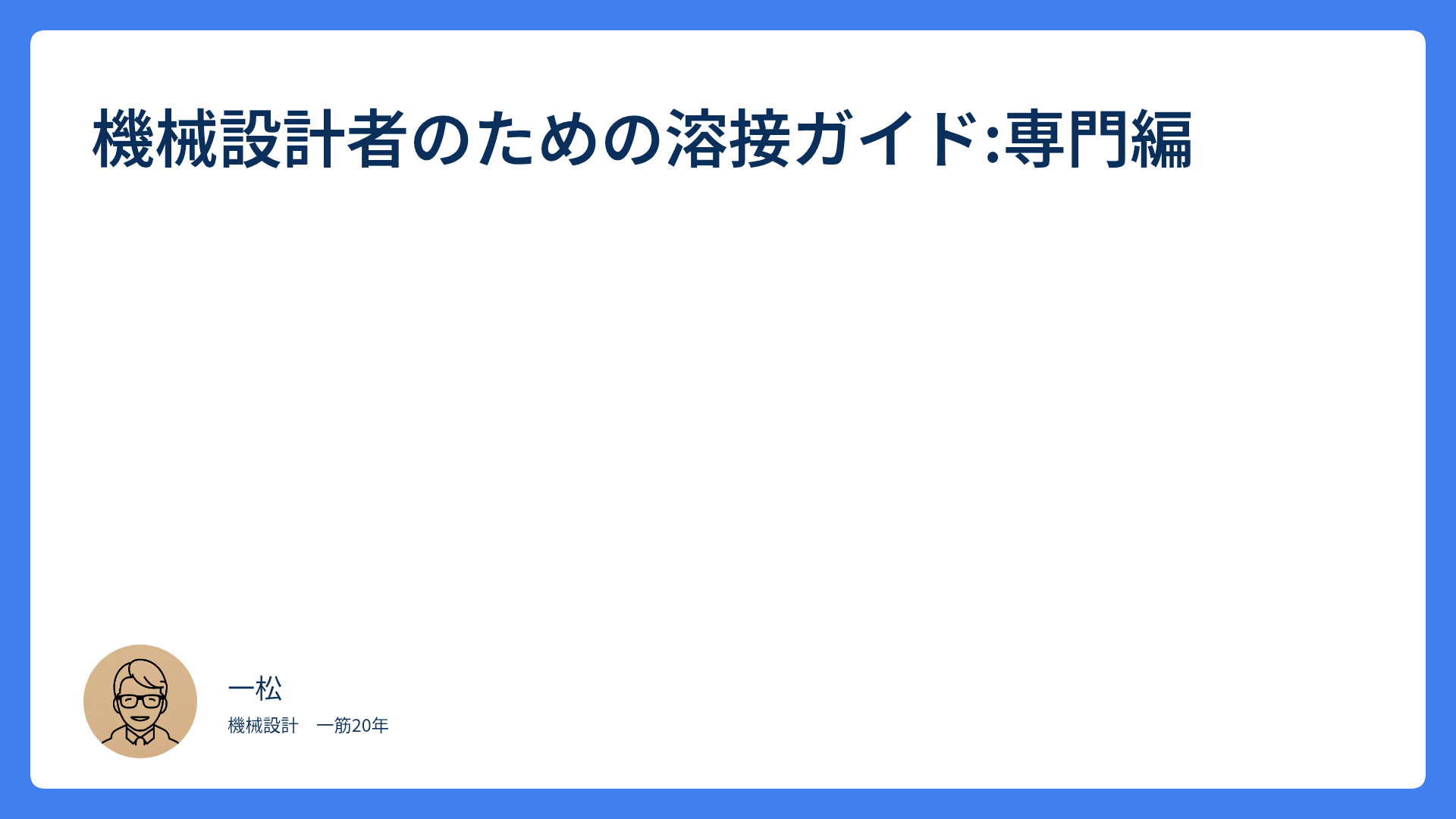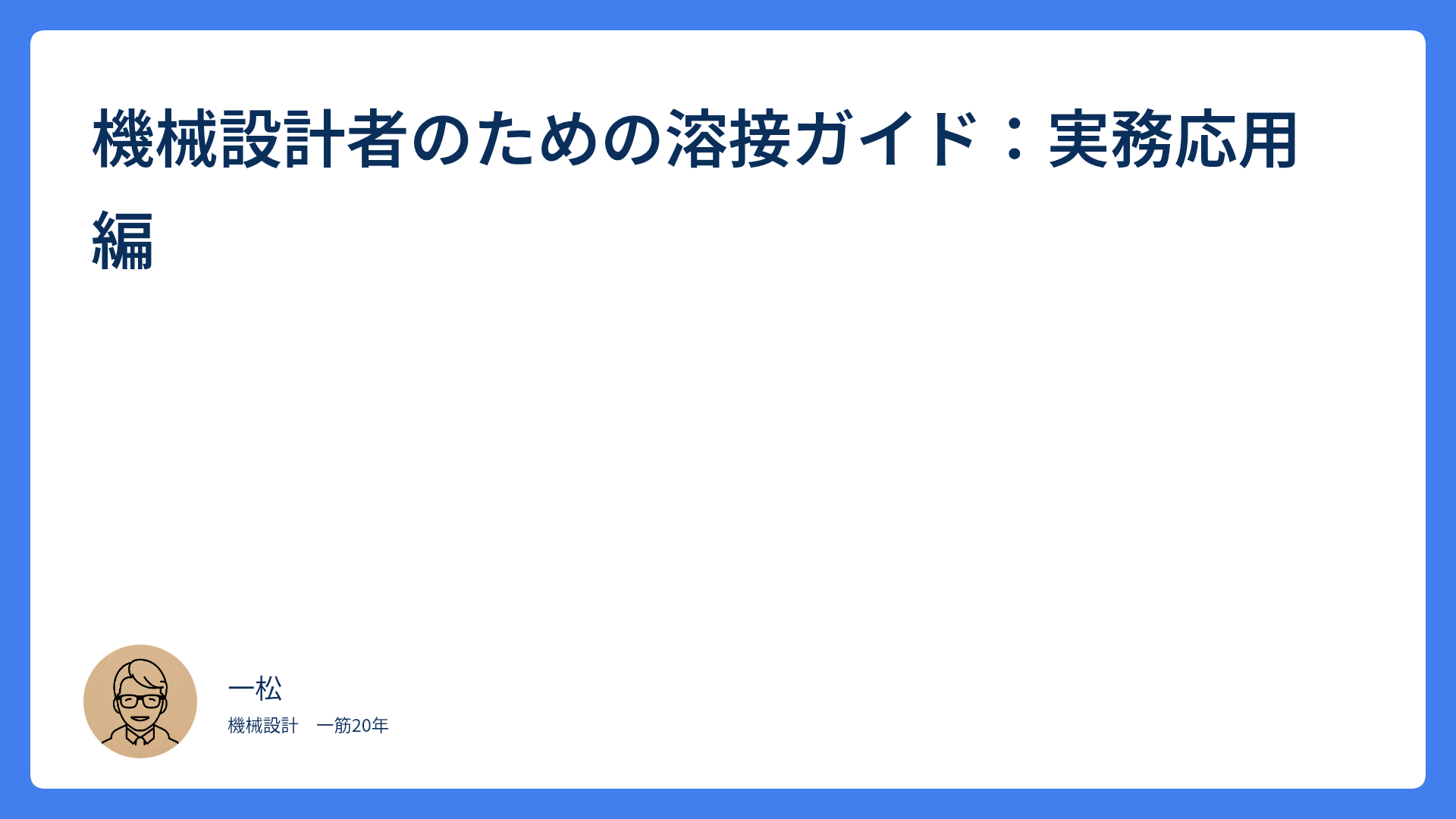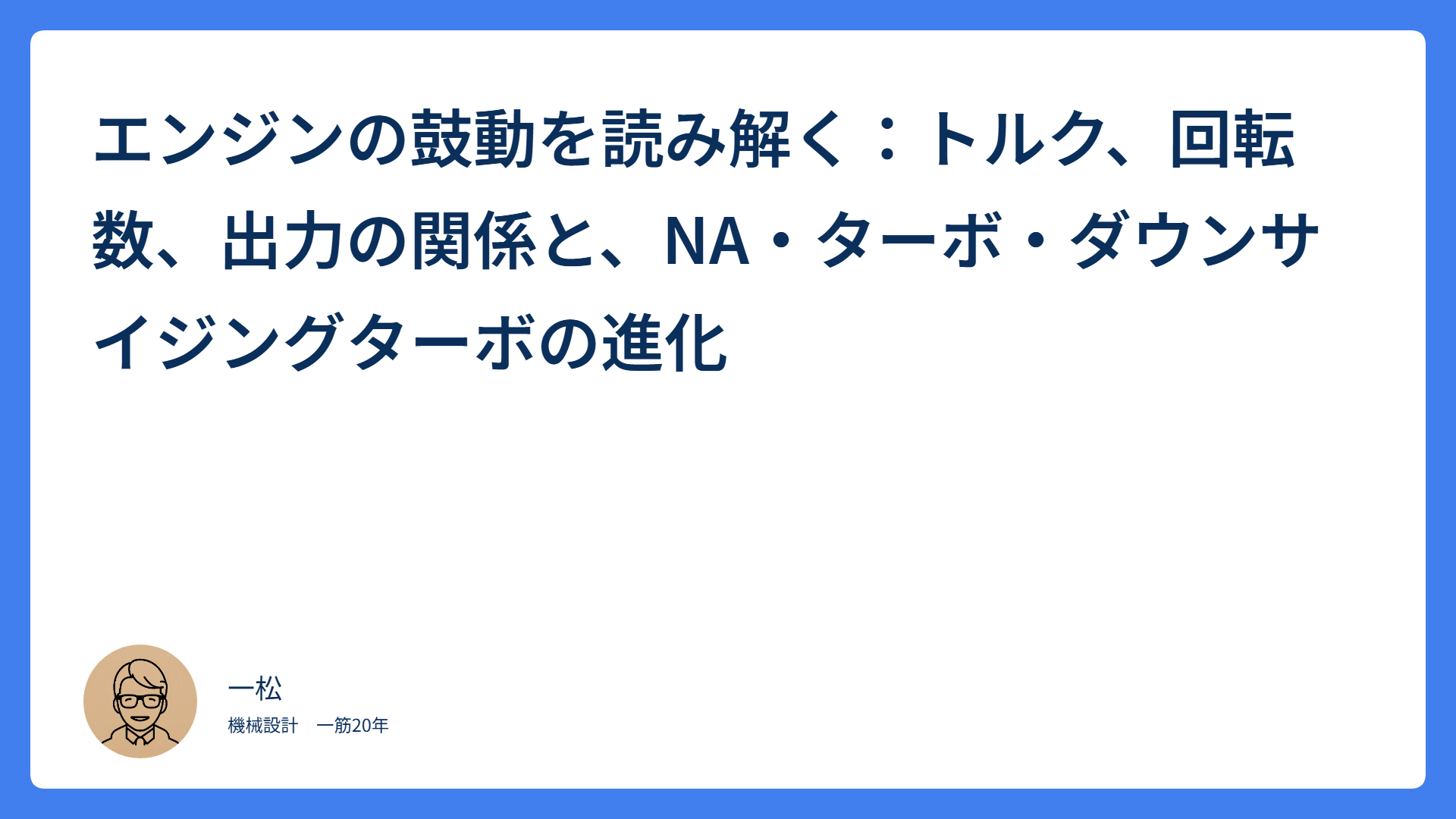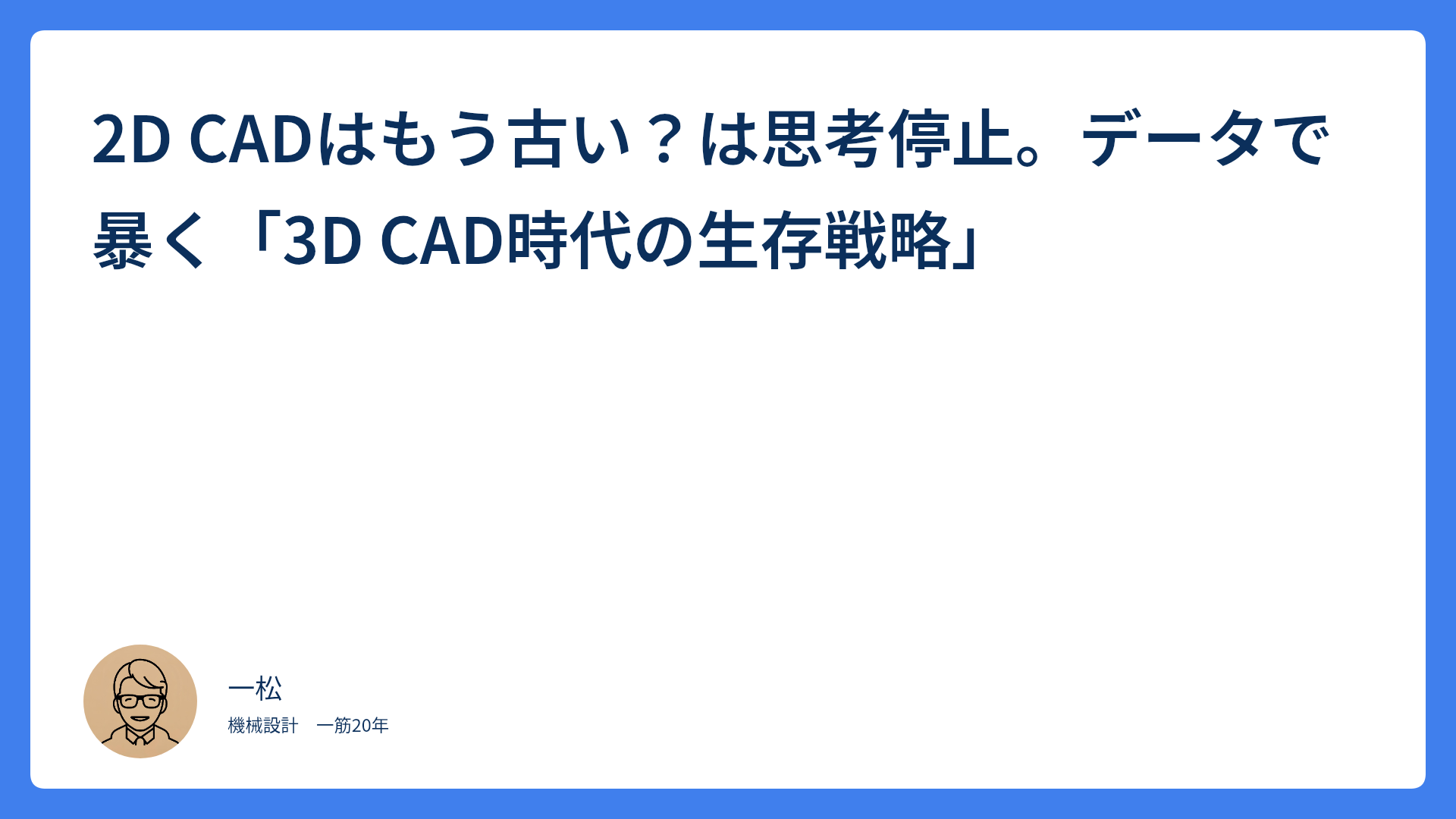予圧が全て:ボルト締結体の「ゆるみ」と「へたり」の物理学とその克服法
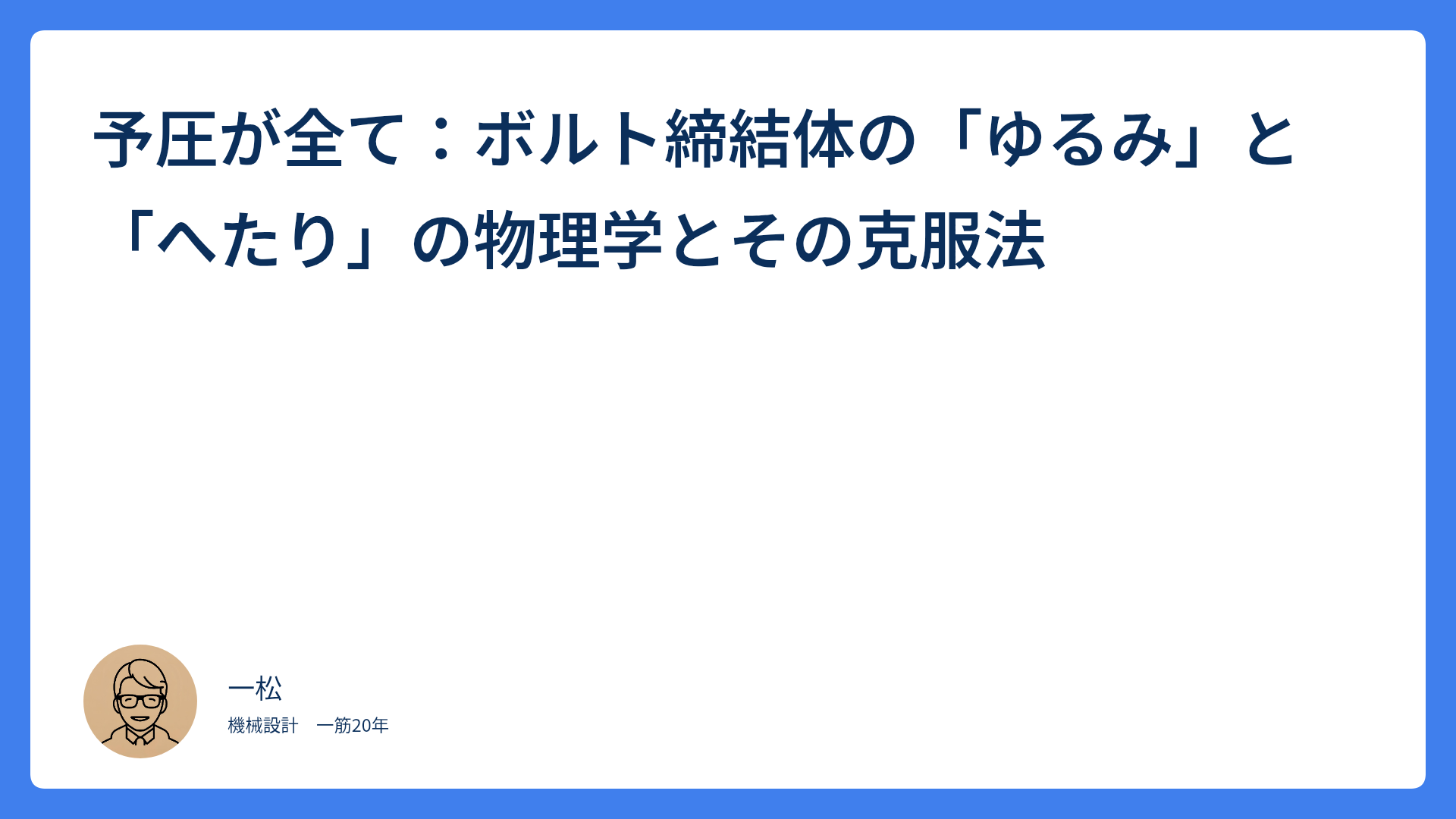
以前の記事「なぜボルトは緩むのか?」では、ボルトが戻り回転してしまう「回転ゆるみ」のメカニズムを解説しました。しかし、実務で遭遇するゆるみは、それだけではありません。
ボルトが全く回転していないにもかかわらず、いつの間にか締結力が失われている――。この静かにかつ確実に進行する「非回転ゆるみ」こそ、多くの設計者が頭を悩ませる問題です。この現象の正体は、「初期なじみ」と「へたり」です。
この記事は、人気記事「なぜボルトは緩むのか?」の続編として、締結信頼性のキーポイントである「軸力(予圧)」をいかに維持するかに焦点を当てます。非回転ゆるみの現象を理解し、克服するための具体的な設計・管理手法を深掘りしていきましょう。
非回転ゆるみの正体:見えざる2つの敵
非回転ゆるみとは、ボルトやナットが回転することなく、締結体の軸力が時間とともに低下していく現象です。その主な原因は2つあります。
- 初期なじみ(Initial Settling): 締結直後に発生する、接触面の微小な塑性変形。
- へたり(Settling/Relaxation): 長期的な荷重や熱の影響で発生する、材料の永久変形。これには「クリープ」と「応力緩和」が含まれます。
これらの現象は、締結された部品間の距離をわずかに縮めることで、引き伸ばされていたボルトの「伸び」を減少させます。ボルトの軸力は、この「伸び」によって生み出されるバネの力そのものですから、伸びが失われれば、軸力も低下してしまうのです。
1. 初期なじみ:締結直後に始まる「微小な圧壊」
ボルトで部品を締め付けるとき、座面や被締結部材の接触面は、見た目には滑らかでも、ミクロのレベルでは無数の微小な凹凸で覆われています。
締結の瞬間、これらの凹凸の先端部分には、極めて高い接触圧力がかかります。この圧力によって、凹凸の先端は塑性変形、つまり押し潰されてしまいます。この微小な圧壊が「初期なじみ」です。
このなじみは、締結直後や、運転開始後の初期の振動・荷重サイクルで特に顕著に発生します。接触面の凹凸が潰れることで、ボルトの軸方向の寸法がわずかに縮み、その結果として初期の軸力低下を引き起こすのです。これが、しばらく使用した機械のボルトを「増し締め」すると、さらに締まることがある理由の一つです。
2. へたり:時間と熱が引き起こす材料の「降伏」
初期なじみが落ち着いた後も、軸力は時間とともにゆっくりと低下し続けます。これが「へたり」であり、その背後には「クリープ」と「応力緩和」という、より深刻な材料の挙動が隠されています。
クリープ現象(Creep)
クリープとは、材料が降伏点を下回る一定の応力を受け続けた状態で、時間とともに永久変形(塑性変形)が進行していく現象です。特に高温環境下で顕著になります。
ボルト締結体においては、ボルト自身よりも、ガスケットのような柔らかい被締結材で問題になることが多くあります。高い面圧を受け続けるガスケットが、時間とともにゆっくりと潰れて薄くなっていくことで、締結全体の寸法が縮み、軸力が失われていきます。
応力緩和(Stress Relaxation)
応力緩和は、クリープと表裏一体の現象です。材料に一定の「ひずみ(伸び)」を与えた状態で保持すると、時間とともに内部の「応力」が低下していく現象を指します。
これはまさに、引き伸ばされた状態で固定されているボルトに起こる現象です。ボルトの弾性変形(元に戻ろうとする変形)の一部が、時間と熱の影響で塑性変形(元に戻らない永久変形)へと変化していくことで、軸力(応力)が徐々に失われていくのです。
ゆるみを克服するためには!?
非回転ゆるみのメカニズムを理解した上で、それを防ぐための具体的な対策を見ていきましょう。
1. 締結管理方法の選択:トルク法は万能ではない
軸力をいかに正確に管理するかは、ゆるみ対策の基本です。主な管理方法には3つありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
- トルク法: 最も一般的で簡単な方法。しかし、入力したトルクの約90%は摩擦(ねじ面と座面)で失われ、実際に軸力に変換されるのは約10%に過ぎません。摩擦係数は表面状態によって大きくばらつくため、同じトルクで締めても軸力には大きなばらつきが生じるという欠点があります。
- 回転角法: ねじが着座してから、さらに規定の角度だけ回して締め付ける方法。ボルトの伸びと回転角が比例関係にあることを利用しており、トルク法よりもはるかに正確な軸力管理が可能です。ただし、設計計算を誤るとボルトを塑性域まで伸ばしてしまい、再利用できなくなるリスクがあります。
- 軸力直接測定法: 超音波軸力計などを用いて、ボルトの伸びを直接測定する方法。最も高精度ですが、コストや手間がかかるため、極めて重要な箇所の締結に限られます。
2. 複合的な要因(外力・熱)を考慮した設計
実際の機械では、ボルト締結部は単に静的な荷重を受けるだけでなく、運転に伴う外力や熱といった複合的な要因に常に晒されています。これらを考慮しない設計は、予期せぬ軸力低下を招きます。
外力による塑性変形のリスク
ボルト締結の基本は、初期に与えた軸力(予圧)が、運転中に加わる外力(部品を引き離そうとする力)よりも常に大きい状態を保つことです。しかし、衝撃的な外力が加わった場合など、瞬間的に「外力+初期軸力」の合計がボルトの降伏点を超えてしまうことがあります。
このとき、ボルトは弾性域を超えて塑性変形、つまり永久に伸びてしまいます。その後、外力が取り除かれると、ボルトは伸びたまま元の長さに戻らないため、結果として初期に設定した軸力が大幅に失われ、ゆるみにつながるのです。
熱サイクルとの複合作用
運転中に温度変化が激しい環境では、事態はさらに複雑になります。ボルトと被締結材の熱膨張係数が異なると、昇温時に両者の伸びに差が生じ、軸力が大きく変動します。例えば、鋼製ボルトでアルミ部品を締結した場合、アルミの方が大きく膨張するため、昇温時に軸力が異常に上昇し、ボルトや被締結材を塑性変形させてしまう可能性があります。
そして、この状態で外力が加わると、ボルトはさらに引き伸ばされ、塑性変形が助長されます。その後、冷却・除荷されると、塑性変形した分だけ元の寸法に戻らず、結果として致命的な軸力低下を招くのです。
【対策】
- 可能な限り、熱膨張係数が近い材料同士を組み合わせる。
- 皿ばね座金(ベルビルワッシャー)などを利用し、締結体全体に弾性を持たせることで、熱膨張・収縮による寸法変化を吸収させ、軸力の変動を緩和する。
- 設計段階で、運転中の外力と温度変化を正確に予測し、それらが複合的に作用した際の最大応力がボルトの降伏点を下回るように、十分な安全率を見込む。
ケーススタディ:エンジンのシリンダーヘッドボルト
これら全ての要因が凝縮された、最も過酷なボルト締結の例が、エンジンのシリンダーヘッドです。
シリンダーヘッドは、燃焼室の爆発圧力(巨大な外力)を封じ込め、同時に高温の冷却水やエンジンオイルの漏れを防ぐという極めて重要な役割を担っています。ここには、これまで述べてきた軸力低下の要因がすべて存在します。
- 初期なじみ: ヘッド、ブロック、ガスケットの各接触面で発生。
- クリープ: 高温高圧に晒されるヘッドガスケットは、時間とともにへたり(クリープ変形)が進行する。
- 応力緩和: 高温に晒されるヘッドボルト自身にも応力緩和が発生する。
- 熱サイクルと外力: エンジンの運転・停止に伴う激しい温度変化と、燃焼による周期的な衝撃荷重が同時に作用する。
このような過酷な環境下で長期にわたりシール性を維持するため、シリンダーヘッドボルトの締結には「塑性域回転角法」という特殊な方法が用いられます。これは、あえてボルトを降伏点を超えた塑性域まで引き伸ばして締め付ける方法です。塑性域では、回転角に対する軸力の変化が穏やかになるため、摩擦係数のばらつきの影響を受けにくく、複数のボルトを極めて均一かつ安定した高い軸力で締め付けることが可能になります。もちろん、一度塑性変形させたボルトは再利用できません。
この例は、ゆるみの各メカニズムを理解し、それらが複合的に作用する現実を直視した上で、最適な締結方法を選択することの重要性を示しています。
まとめ:締結は「固定」ではなく「管理」である
ボルト締結の信頼性は、「締めたら終わり」ではありません。締結直後の「初期なじみ」から、外力や熱がもたらす塑性変形、そして長期的な「へたり」に至るまで、軸力は常に失われる方向へと変化し続けています。
真に信頼性の高い設計とは、これらの目に見えない物理現象を理解し、予測し、そしてコントロールすることに他なりません。締結方法を適切に選び、材料の特性を理解し、外力や熱の複合的な影響を考慮する。こうした地道な積み重ねこそが、ボルト締結体を単なる「固定具」から、長期にわたって機能を維持する「精密な弾性システム」へと昇華させるのです。