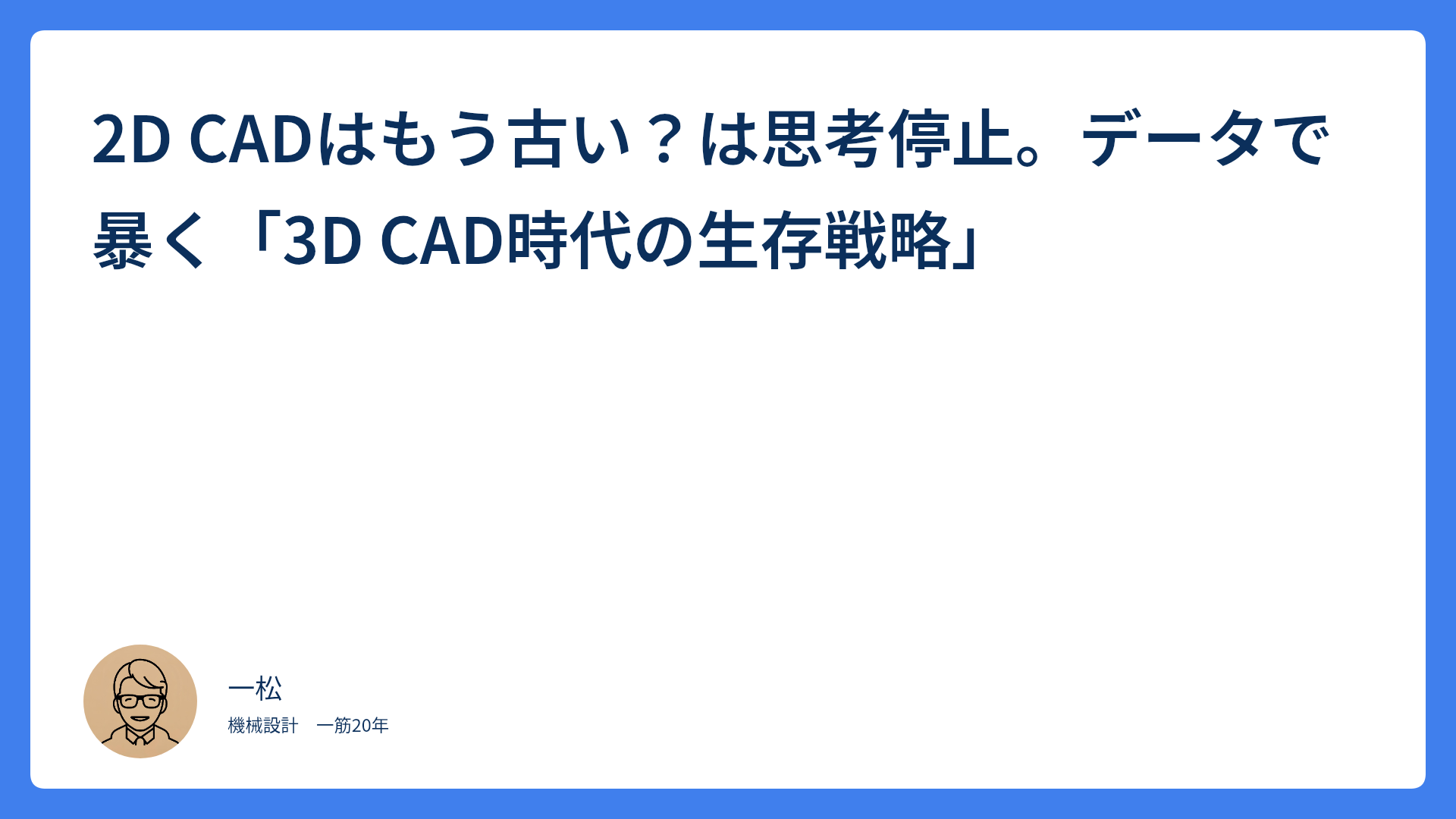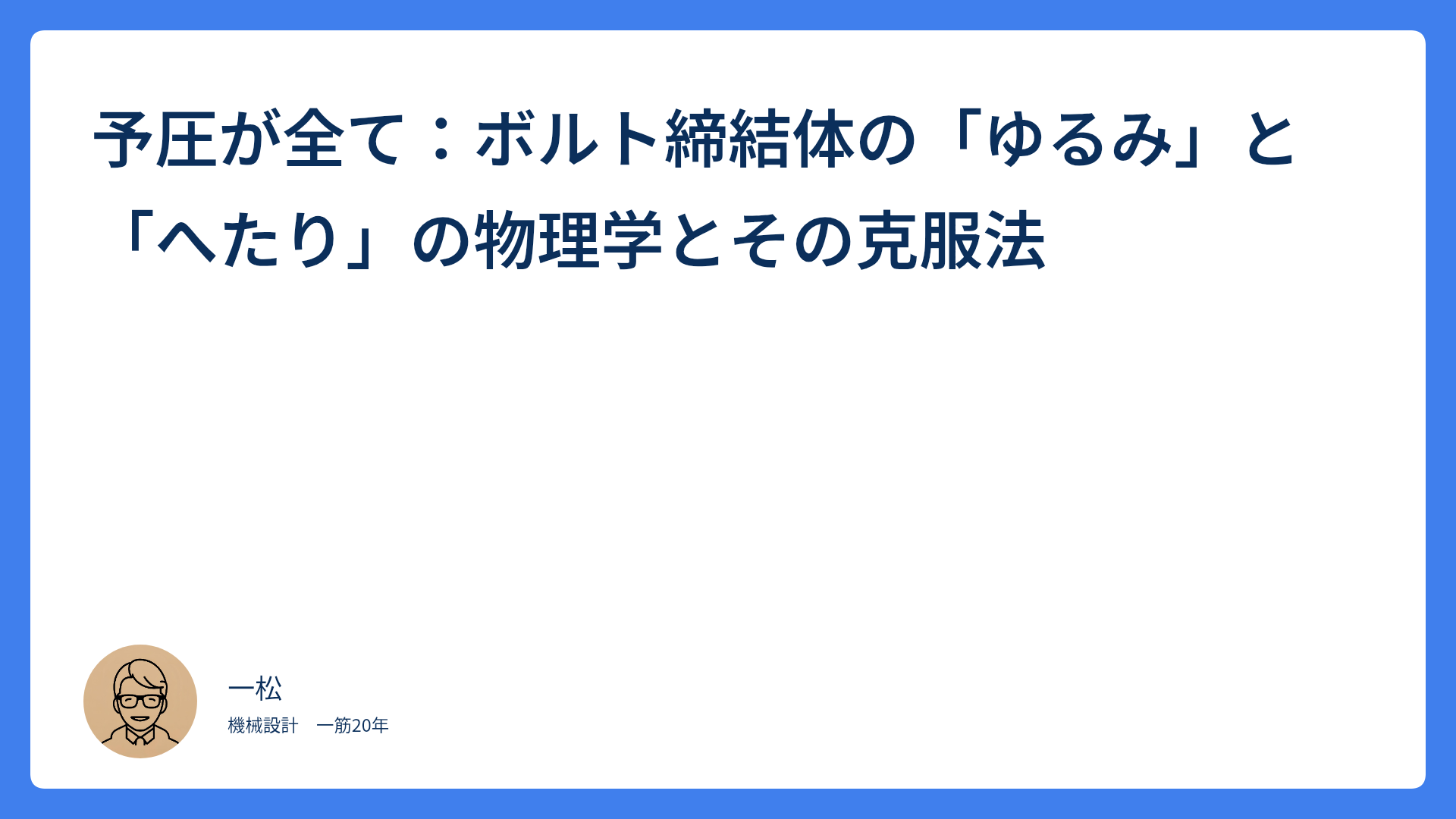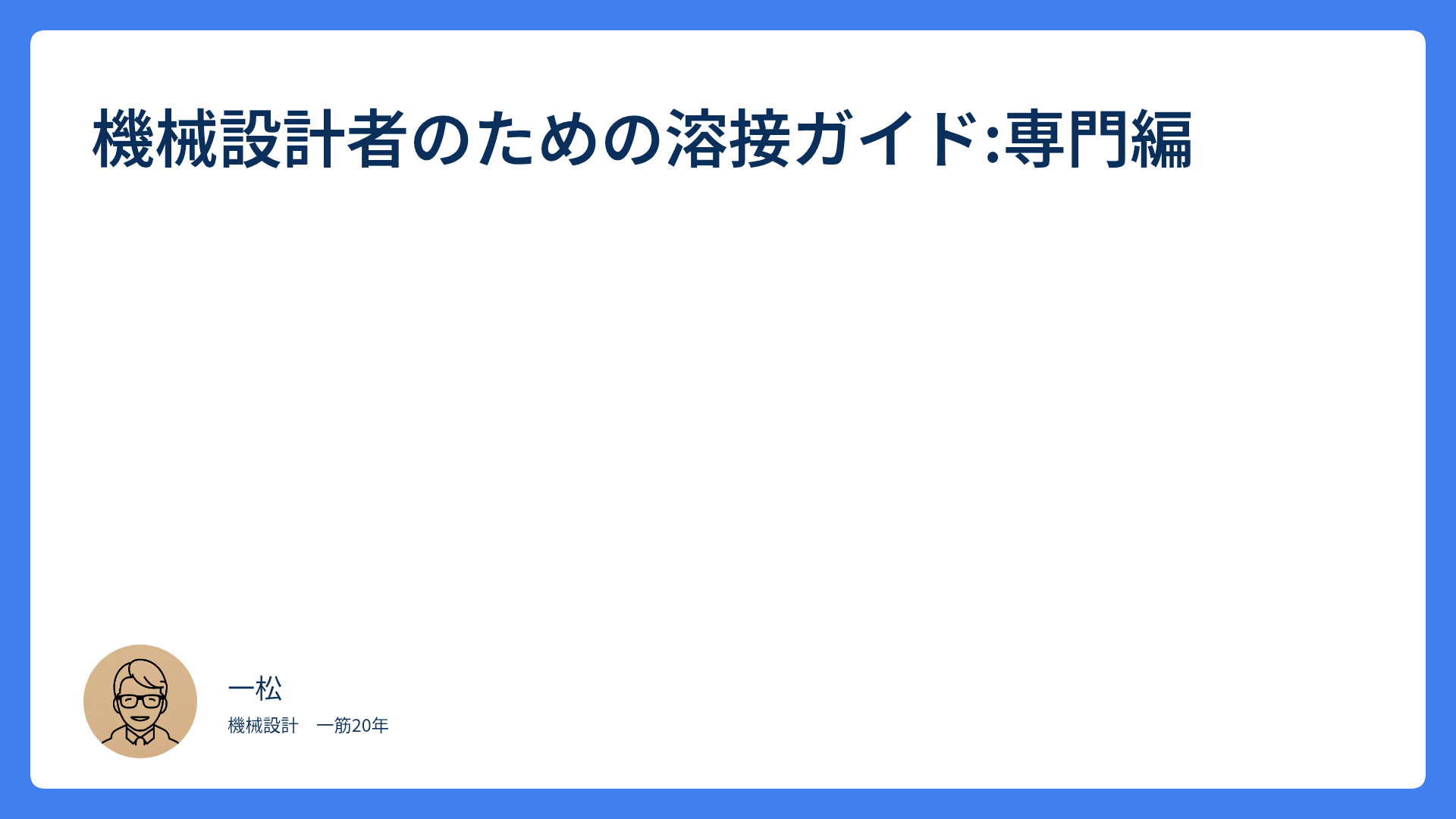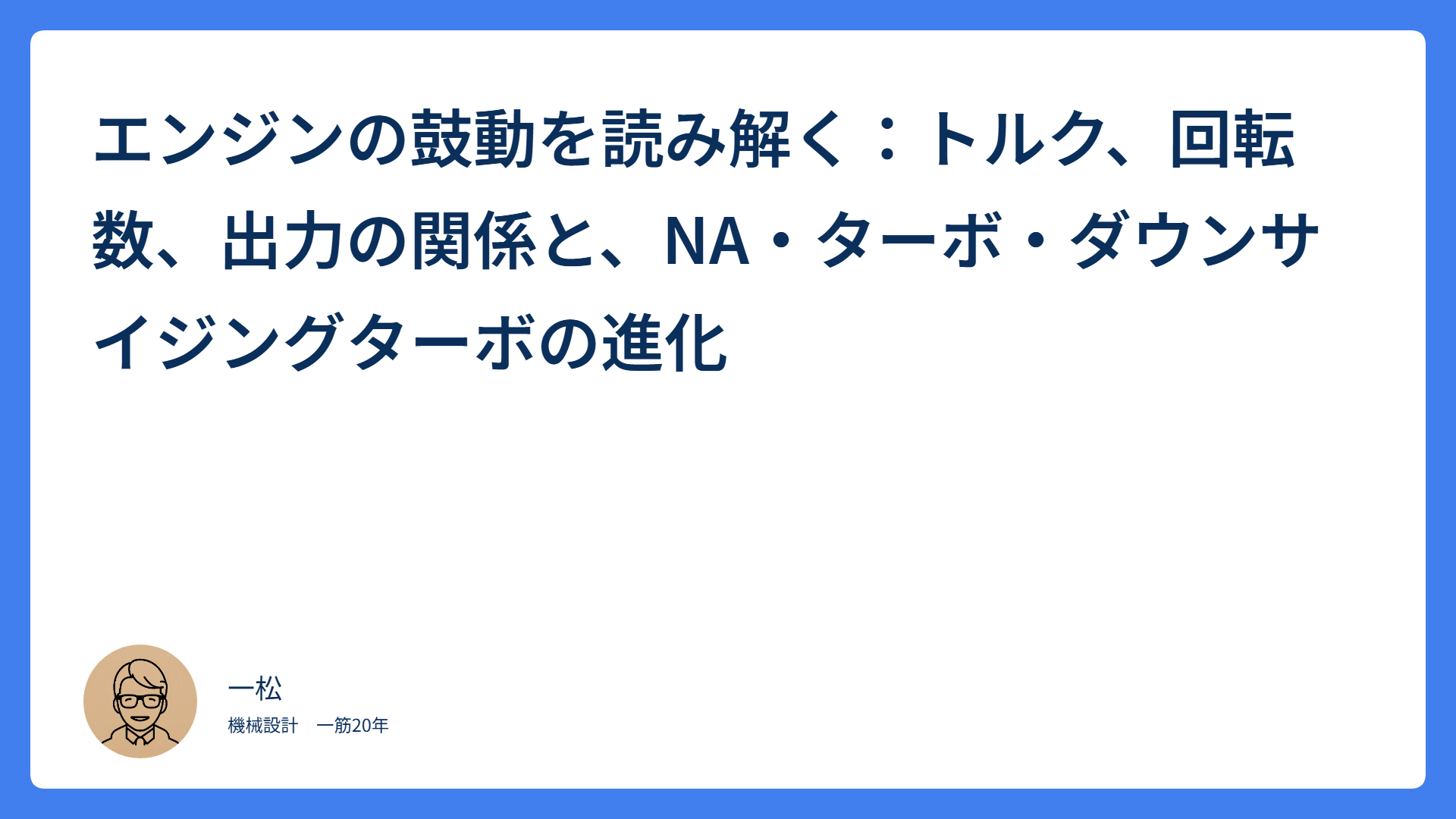機械設計者のための溶接ガイド:実務応用編
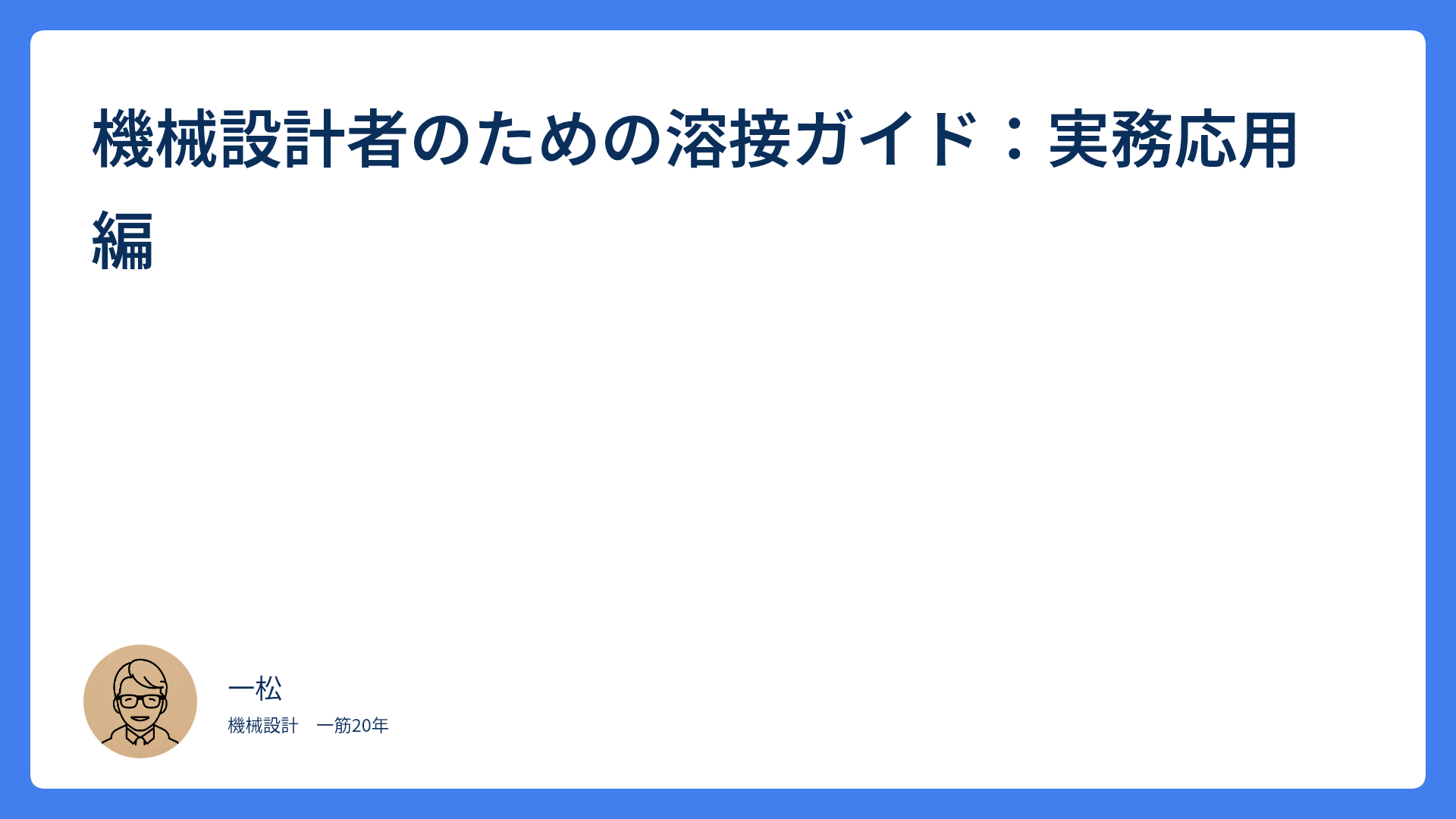
はじめに:設計で「品質」と「コスト」を作り込む
【入門編】では溶接の基本と種類を学びました。しかし、実務で設計者が本当に価値を発揮するのは、ここからです。溶接構造の品質は、製造現場の腕だけに依存するものではありません。むしろ、設計段階で「いかに強度を確保し、変形を抑えるか」を織り込めるかが、製品の性能とコストを決定づけます。
この記事は、溶接の基礎を理解した設計者が、次のステップに進むための実務応用編です。溶接設計における最大の課題である「熱歪み」のコントロール方法、必要な強度を確保するための計算、そして設計意図を製造現場に100%伝えるための「溶接記号」のルールまで、現場で即使える実践的な知識を深掘りします。理論を設計に落とし込み、”作れる”設計者を目指しましょう。
第1章:溶接最大の敵「熱歪み」をコントロールする設計
1.1 なぜ歪むのか?そのメカニズム
溶接で部材が歪むのは、「加熱された部分が冷えて縮む」という単純な物理現象が原因です。しかし、その過程は少し複雑です。
- 加熱と膨張: 溶接部は超高温になり、膨張しようとします。
- 周囲からの拘束: しかし、周りの冷たい母材がガッチリ固めているため、自由に膨張できません。
- 圧縮変形: 行き場を失った膨張力は、高温で柔らかくなった溶接部自身を押し潰す力(圧縮塑性変形)として作用します。
- 過剰な収縮: 溶接が終わり冷える際、溶接部は元のサイズに戻るだけでなく、押し潰された分だけ余計に縮もうとします。
- 歪みと残留応力の発生: この「余計な収縮」が、部材全体を引っ張り、曲げたり反らせたりする力(=歪み)となって現れるのです。
1.2 歪みを減らすための4つの設計原則
このメカニズムがわかれば、対策は自ずと見えてきます。歪みを抑えるには、以下の設計原則が非常に有効です。
- 原則1:溶接量は最小限に: 歪みの大きさは、溶かした金属の量に比例します。強度的に問題ない範囲で、溶接のサイズ(後述する「脚長」など)はできるだけ小さく設計するのが鉄則です。
- 原則2:対称に配置する: 部材の中心線に対して、溶接箇所を左右対称・上下対称に配置すると、収縮する力が互いに打ち消し合い、歪みを大幅に抑制できます。
- 原則3:溶接順序を考慮する: 熱が1箇所に集中しないよう、溶接の順番を工夫することも重要です(例:対称な箇所を交互に溶接する、飛び石のように間隔をあけて溶接する)。これは設計者が図面で指示することもあります。
- 原則4:治具で拘束する: 溶接中に部材が動かないよう、強固な治具で物理的に固定する方法です。ただし、変形を無理に抑え込むと、部材内部に大きな力(残留応力)が残るため注意が必要です。
第2章:壊れない製品を作るための強度設計
2.1 最もよく使う「すみ肉溶接」の強度計算
T字やL字の継手で使われる「すみ肉溶接」は、実務で最も頻繁に登場します。この強度を考える上で重要なのが「脚長(きゃくちょう)」と「のど厚(のどあつ)」です。
- 脚長 (S): 溶接ビードの断面を直角二等辺三角形と見なしたときの、等しい辺の長さ。設計者が図面で指示するサイズです。
- のど厚 (a): 溶接断面で最も短い距離。実際に力がかかる有効な厚みであり、強度計算の基礎となります。
脚長Sとのど厚aには、以下の関係があります。
この「のど断面」がせん断力に耐えると考え、溶接部が負担できる荷重Pは次のように概算できます。
設計者にとって重要なのは、脚長Sを1mm増やすと、溶接量は2倍近く増え、コストと歪みも大幅に増大するという事実です。「念のため大きく」という安易な指示は避け、計算に基づいて必要最小限の脚長を指示することが、優れた設計の基本です。
2.2 精度が欲しい場所は「後加工」を前提にする
溶接は、どんなに工夫してもミクロン単位の精度を出せる加工方法ではありません。ベアリング穴やモーターの取付面など、高い寸法精度が必要な箇所は、「溶接で大まかな形を作り、後から機械加工(フライスや旋盤)で精密に仕上げる」という発想が不可欠です。
これを「後加工」と呼び、設計者は以下の点を図面に盛り込む必要があります。
- 加工代(しろ): 後で削る分を見越して、あらかじめ部品に余分な厚みを付けておく。
- 加工基準: 溶接で歪んだ後でも、どこを基準に削るのか(データム)を明確に指示する。
第3章:設計意図を伝える「溶接記号」のルール
設計者の考えを製造現場に正確に伝えるための言語が「溶接記号 (JIS Z 3021)」です。ここでは、最低限覚えておくべき基本ルールを解説します。
- 基本構成: 溶接記号は、情報を書き込む「基線」、溶接箇所を指す「矢」、補足情報を書く「尾」から成ります。
- 最大のルール: 矢が指している側(手前側)の指示は基線の「下側」に、その反対側(向こう側)の指示は基線の「上側」に書きます。
- すみ肉溶接の指示:
- すみ肉溶接は「▲」で表します。
- 記号の左側に「脚長S」の寸法を書きます。(例:▲の左に「6」と書けば脚長6mm)
- 記号の右側に「溶接長さL」を書きます。
- 便利な記号:
- 全周溶接「○」: 矢と基線の交点に丸を書くと「ぐるっと一周溶接して」という意味になります。
- 現場溶接「⚑」: 同じく交点に旗を書くと「工場ではなく現場で溶接して」という意味になります。
溶接記号は、単なる絵ではありません。コストと品質を直接左右する、法的な拘束力を持つ「仕様書」です。その意味を正確に理解し、正しく使うことが設計者の責任です。
まとめ:実務で活かす設計のポイント
今回の実務応用編では、より具体的な設計手法について学びました。
-
- 溶接歪みは「溶接量を減らす」「対称に配置する」ことでコントロールできる。
- すみ肉溶接の強度は「のど厚」で決まり、「脚長」から計算できる。過剰な指示はコスト増の原因。
– 高精度な部分は「後加工」を前提に、加工代と基準を設ける。
– 溶接記号は、基線の上下で手前/向こう側を区別するルールが最も重要。
これらの知識を駆使することで、あなたの設計はより現実的で、製造しやすく、信頼性の高いものになるはずです。しかし、世の中には様々な金属があり、それぞれに特有の溶接の難しさがあります。次の【専門編】では、材料ごとの注意点や、完成品の品質をどう保証するかといった、さらに深いテーマに踏み込んでいきます。