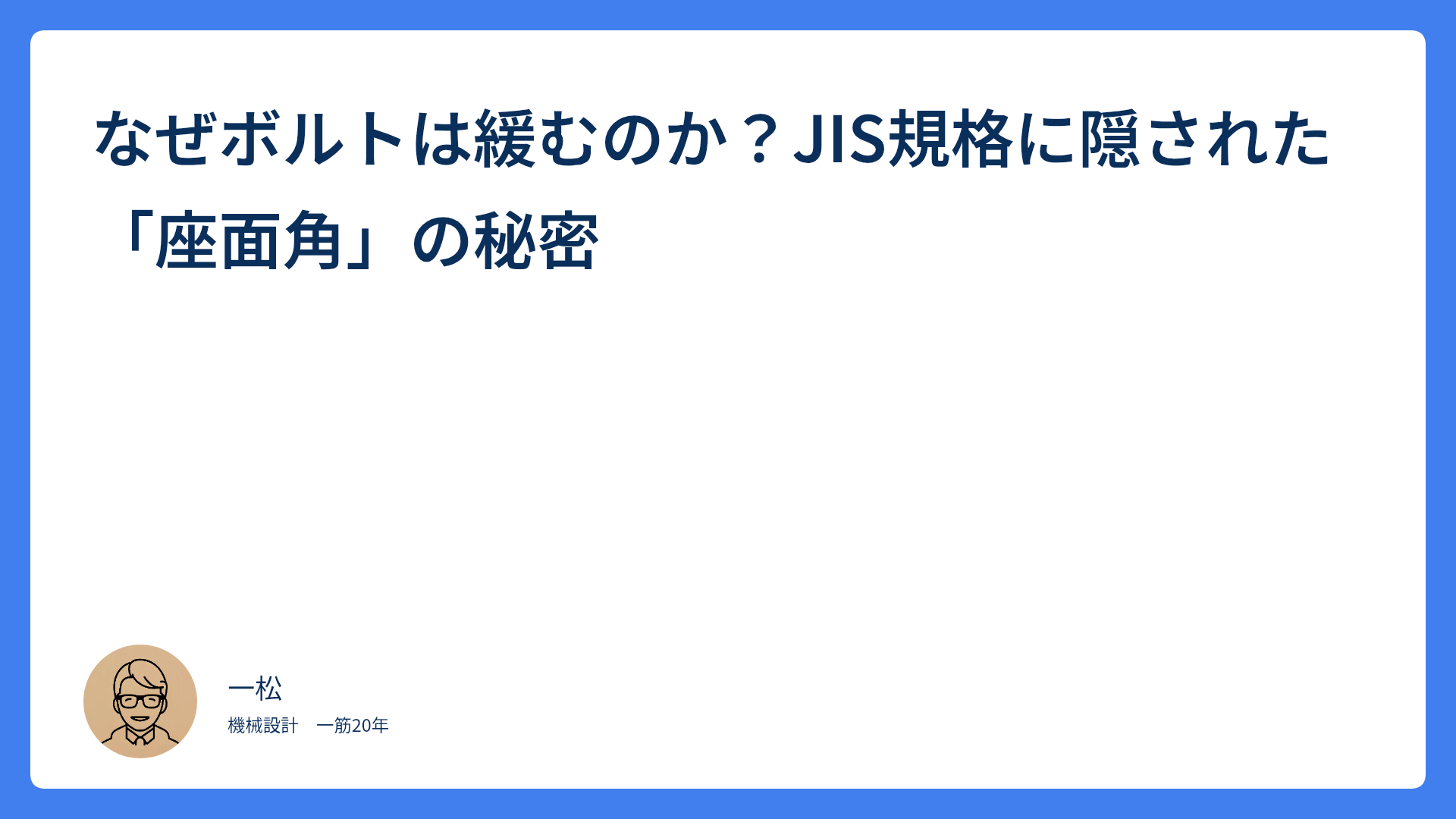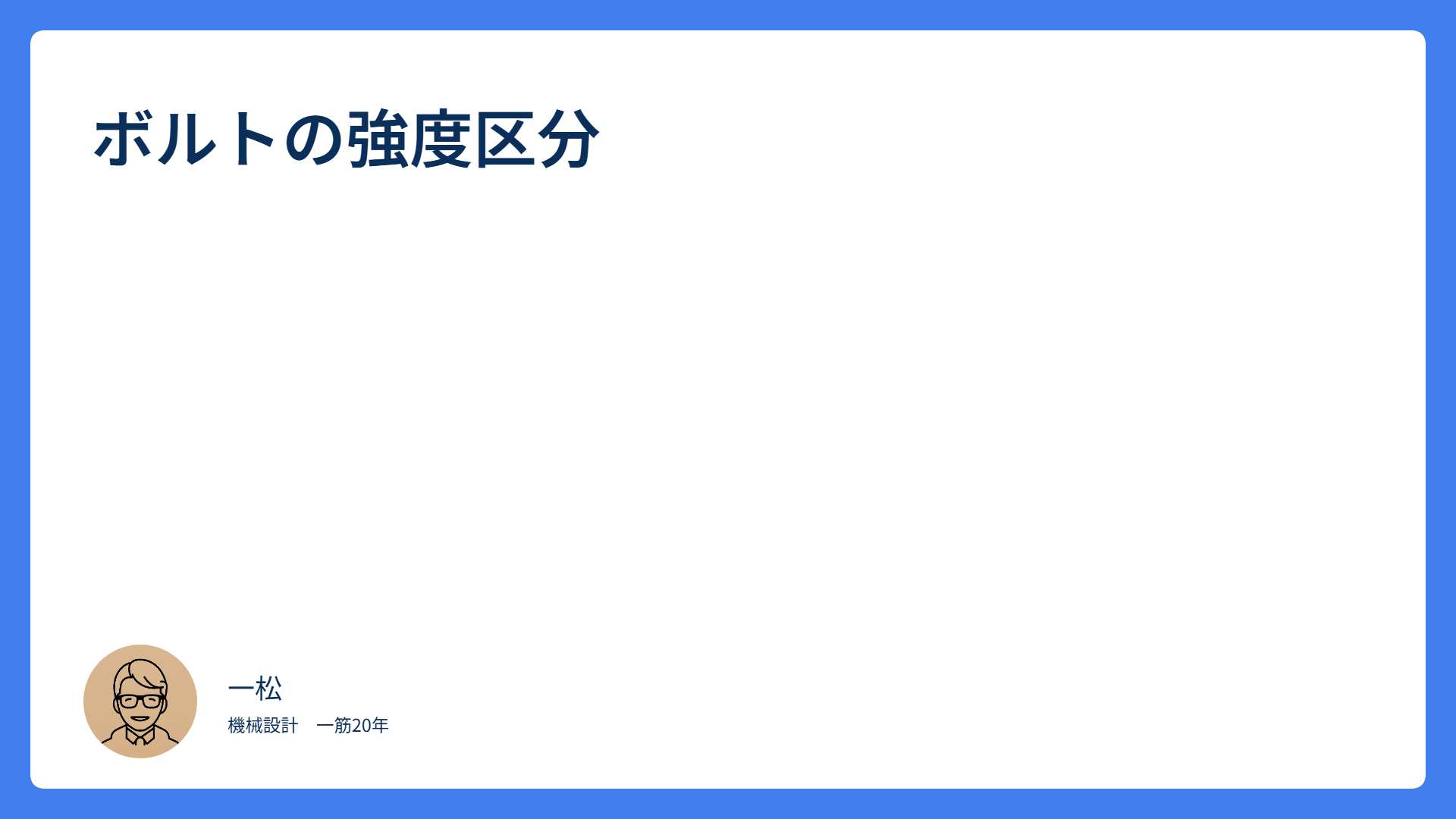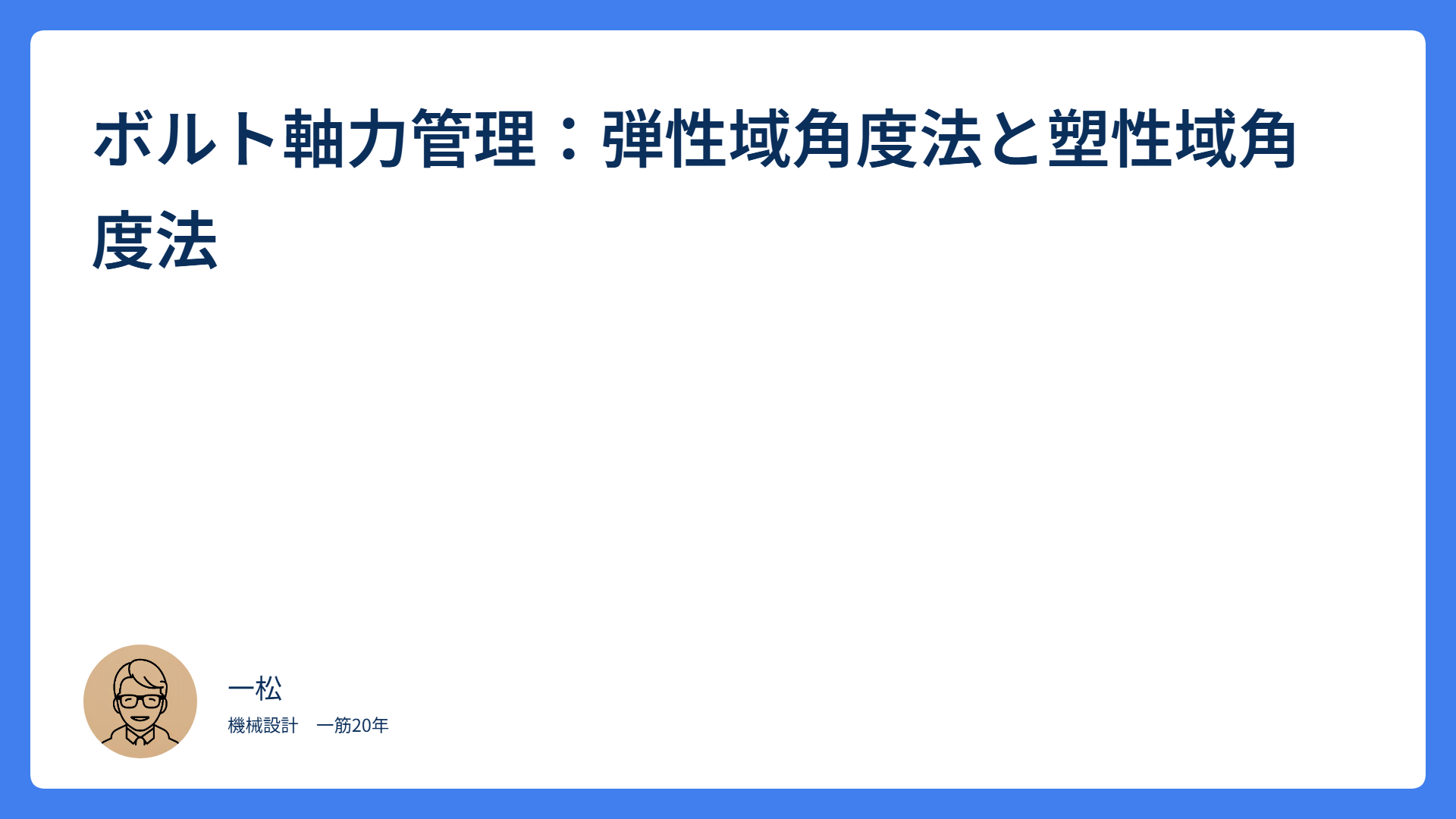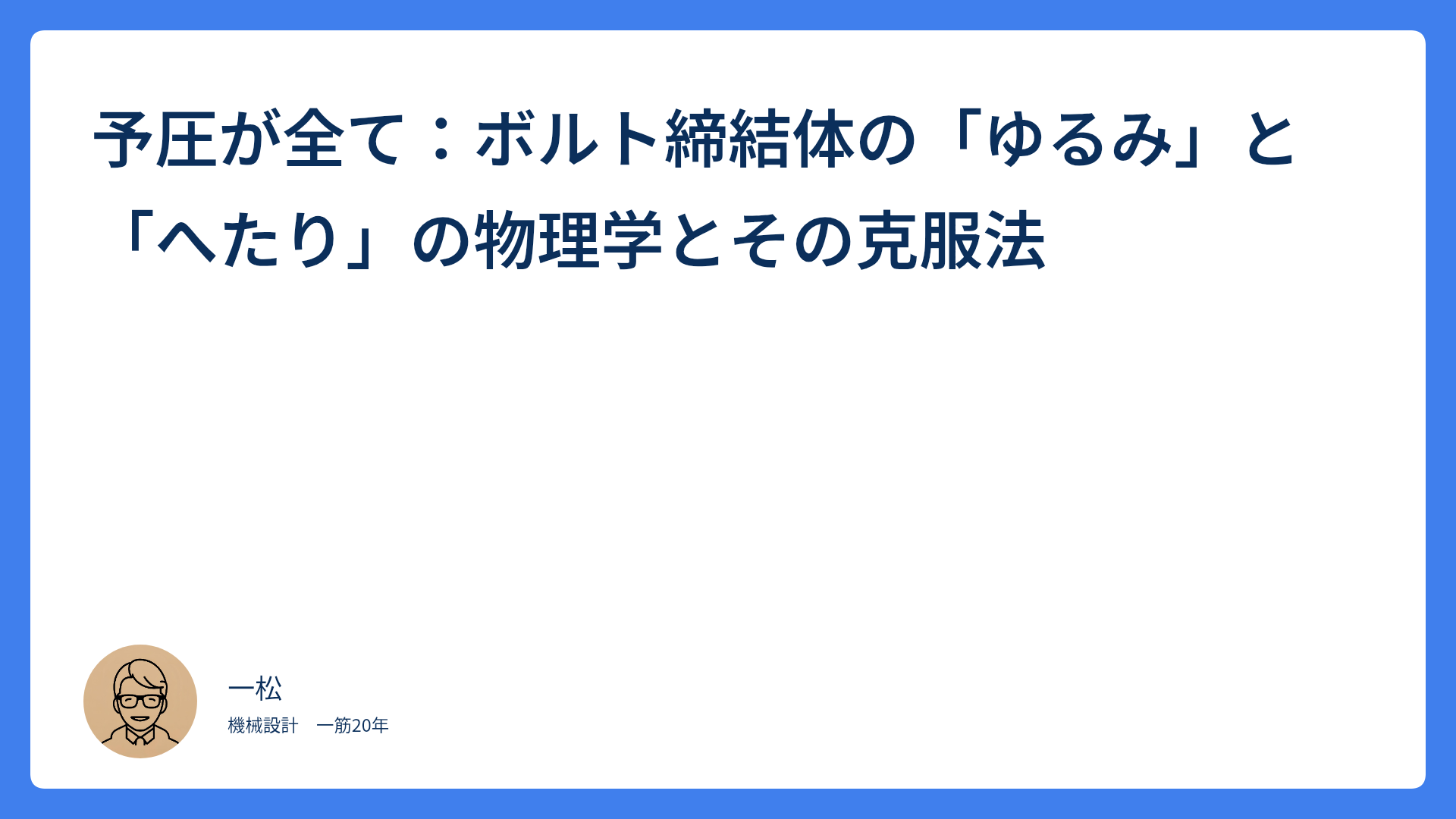締結トルクと軸力について

締結は「ボルトとナットが強く挟み合う力で物が固定されている」
そう思っていませんか? もちろんその答えは間違いではありません。ですが、それはボルト締結の仕組みの半分でしかありません。そのイメージだけだと、思わぬトラブルにつながる設計をしてしまう可能性も…。
この記事では、難しい数式は使わずに、ボルト締結の「仕組み」について、その概念を分かりやすく解説します。
ボルトは「伸びて」固定する
ボルトには「ねじ」が切られていますね。このねじは、らせん状の坂道のようなものです。ボルトを締め付ける(回転させる)と、その力の一部は、ねじの坂道を登るようにしてボルト自身を「伸ばす」力に変換されます。(残りの力は、主に摩擦力として消費されます)
そう、ぎゅっと締め付けられたボルトは、目には見えにくいですが、確実に伸びているのです。
ボルトは強力な「バネ」である
この「伸びているボルト」は、物理学でいう「バネ」と同じように考えることができます。
高校の物理で「バネの力 F=kx」という式を習ったのを覚えていますか?
- F:力(ボルトの場合は軸力と呼ばれます)
- k:バネ定数(バネの硬さ。ボルトの場合は非常に大きい)
- x:伸び(変形量)
ボルトの種類や締め付け具合にもよりますが、x(ボルトの伸び量)は、数十μm(マイクロメートル)から数百μm程度と、非常にわずかです。
しかし、ボルトはバネとして見ると非常に「硬い」ため、k(バネ定数)が非常に大きな値になります。
その結果、わずかな伸びxであっても、F=kx の原理によって、非常に大きな軸力Fが発生するのです。
締結力の主役は「軸力」
この軸力こそが、ボルトとナット、そして締め付けられる部品(非締結物)を強力に押さえつけ、固定する力の「正体」です。
例えば、M6サイズのボルトを考えてみましょう。仮にこのボルトで鉄を10N・m(ニュートンメートル)というトルクで締め付けたとします。この時、ボルトに発生する軸力は数百kgf〜数トンにも達します(摩擦係数によって大きく変動します)。この強い力で部品同士を互いに押し付け合うことで、物がしっかりと固定されるわけです。
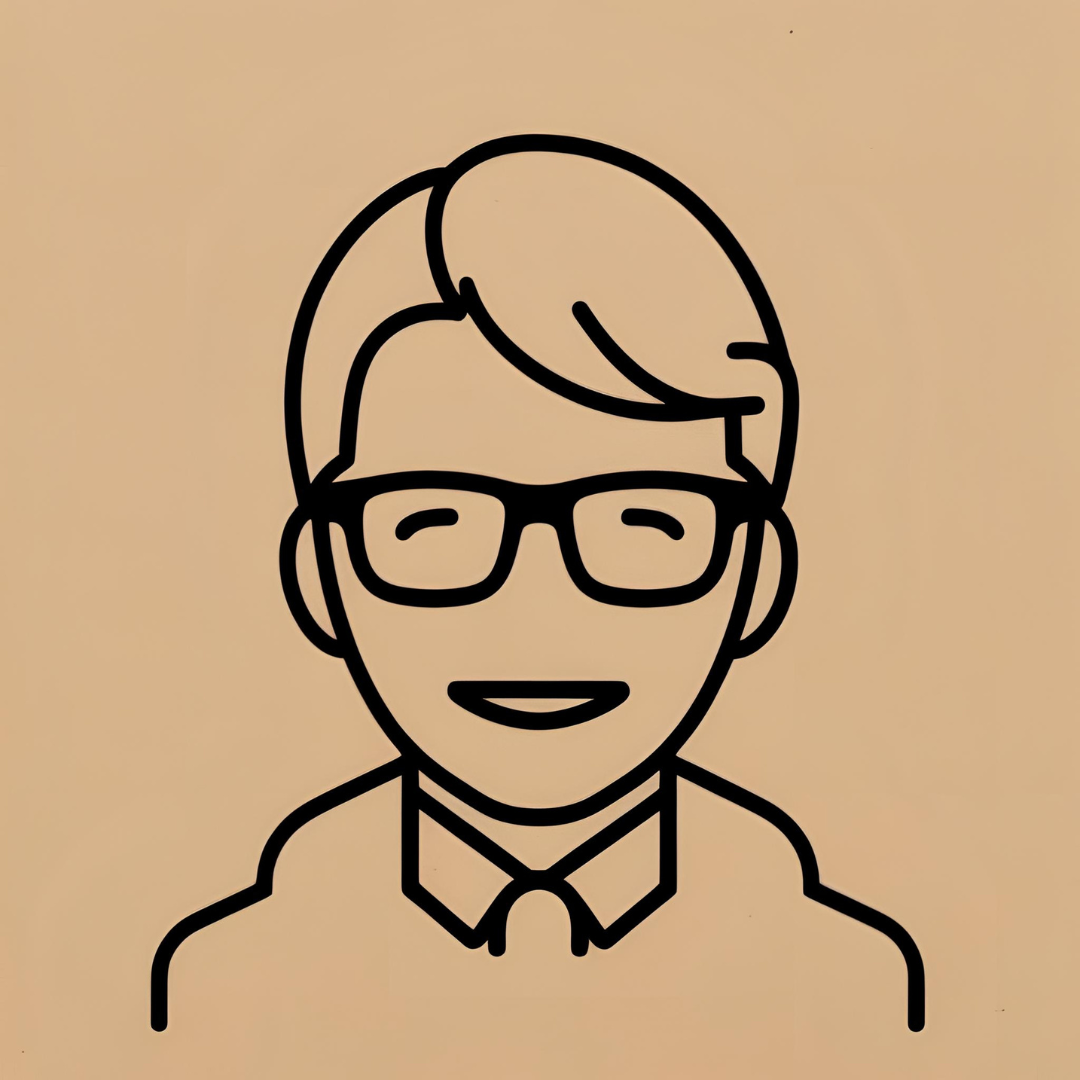
さらっと書きましたが、摩擦係数はねじの締結にとって非常に重要な要素です。摩擦係数の大小は大きな問題ではないのですが、個体差によるばらつきが大きな問題になります。
これについては、別に記事を書きますね
ボルトの「緩み」とは?
ボルトが緩むということは、この重要な「軸力」が低下すること、つまり、ボルトの「伸び」が元に戻ってしまう(減少する)ことを意味します。
「ボルトの緩み」と聞くと、多くの人はボルトが逆回転してしまう「回転緩み」を想像するかもしれません。締め付けを「トルク」で管理していると、このイメージが強くなりがちです。
しかし、緩みの原因はそれだけではありません。
- 非回転緩み:
- 座面の陥没・摩耗: 部品とボルト・ナットが接触する面(座面)が、繰り返しの荷重や振動で潰れたり、すり減ったりして、結果的にボルトの伸びが戻ってしまう。
- 熱膨張差による収縮: 温度変化が大きい環境で、ボルトと部品の材質が違う場合、温められたり冷やされたりした際の伸び縮みの差によって、軸力が変動し、低下することがある。
- 塑性変形: ボルトに設計想定以上の大きな外力が加わり、ボルトが伸びきって元に戻らなくなる(降伏点を超えて塑性変形する)。これも軸力低下につながります。
これらの「非回転緩み」は、ボルト自体が回転していなくても発生します。
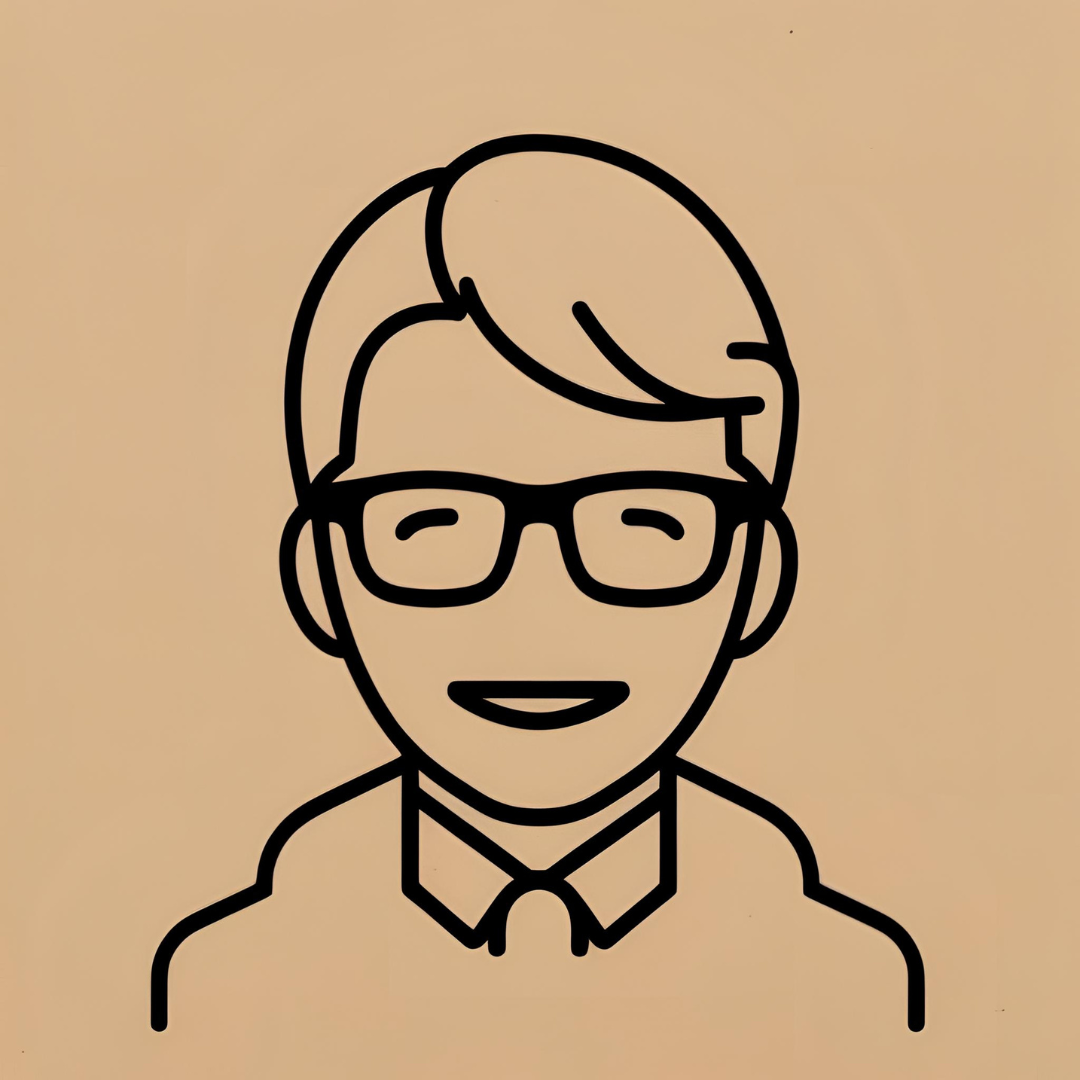
多くの技術者が直面するのは、耐久試験などでトルクが下がる事でしょう。さらにややこしいのが、上記の複数の症状がみられることです。これもよくあることです。
大事なのは、よく現物を見ること。そしてその現象が発生するためにはどういった事象が発生していないと理屈に合わないかを、仮定⇒否定を繰り返して推察することです。
緩み止め対策の注意点
ネジロック剤(嫌気性接着剤)や、緩み止めナット(ロックナット、ハードロックナットなど)といった、一般的な「緩み止め対策」があります。これらは非常に有効な手段ですが、主に「回転緩み」を防ぐことを目的としています。
そのため、ボルトの脱落防止には効果を発揮しますが、上記のような「非回転緩み」が原因で軸力が低下する場合には、必ずしも緩み(=軸力低下)を防ぐ効果があるとは限りません。
締結する目的によっては、単にボルトが脱落しないだけでなく、一定の軸力を維持し続けることが非常に重要になる場合があります。例えば、Oリングなどを使って流体や気体の漏れを防ぐ「面シール」の締結では、軸力が低下するとおOリングを潰す圧力が低下してシール性能が失われてしまいます。このような場合、回転緩み対策だけでは不十分な可能性があるのです。
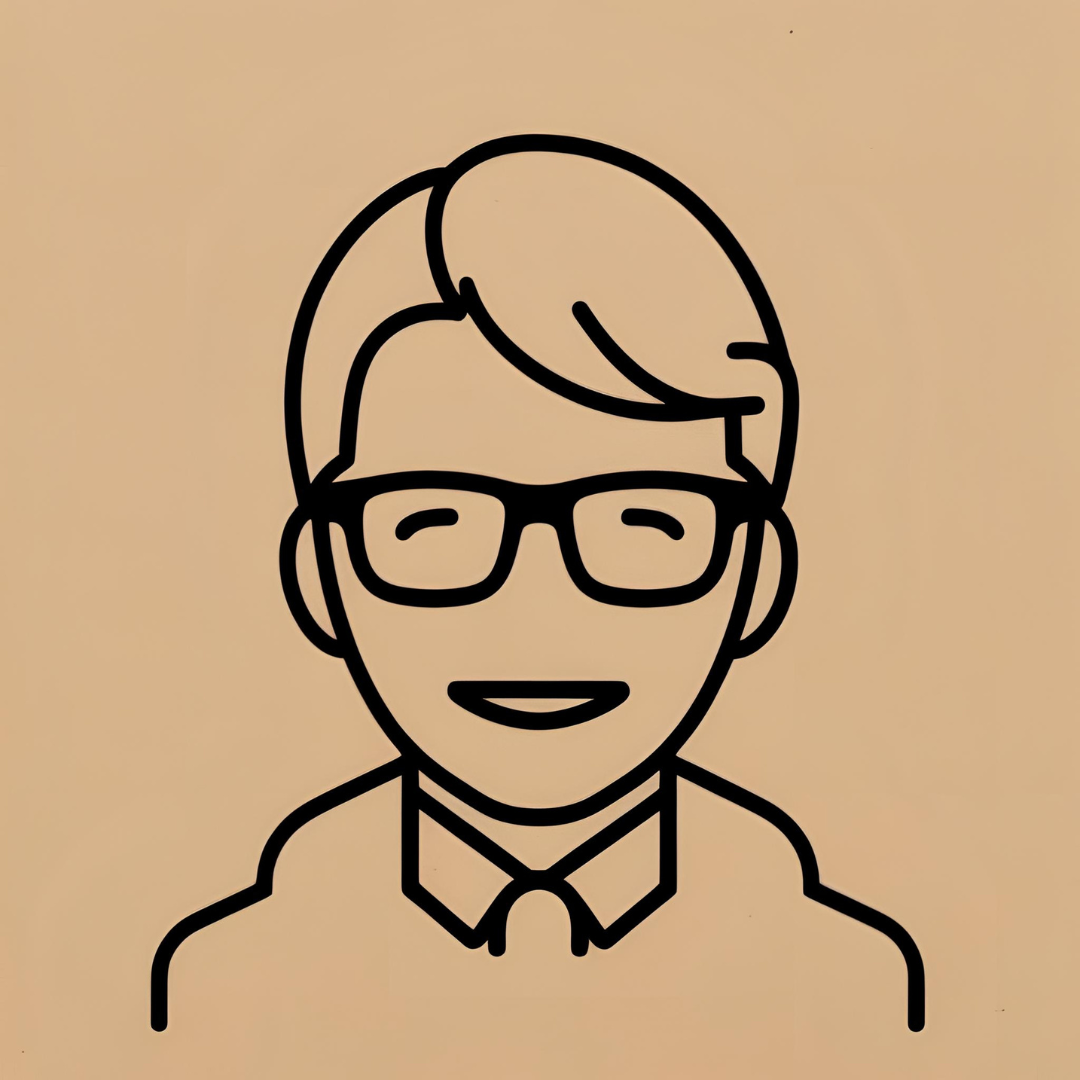
面シールと締結は非常に相性の良い組み合わせですが、同時に相性の悪い組み合わせとも言えます。
例えば、シールをする構成品が被締結物の剛性に関わっている場合(例えばガスケットなど)、その構成品がへたって厚さが薄くなるとその分だけボルトの伸び量が少なくなり緩みにつながります。
その締結する構造体がどの様に使われるかを想定して設計することも、設計の醍醐味ですね!
まとめ
ボルト締結の鍵は、単なる「挟み込み」だけではなく、ボルト自身の「伸び」によって生み出される「軸力」にあります。そして、「緩み」とは、この軸力が低下することです。
なぜ緩むのか、その原因(回転か、非回転か)を正しく理解し、目的に合った適切な設計や緩み対策を選ぶことが、安全で確実な締結には不可欠です。