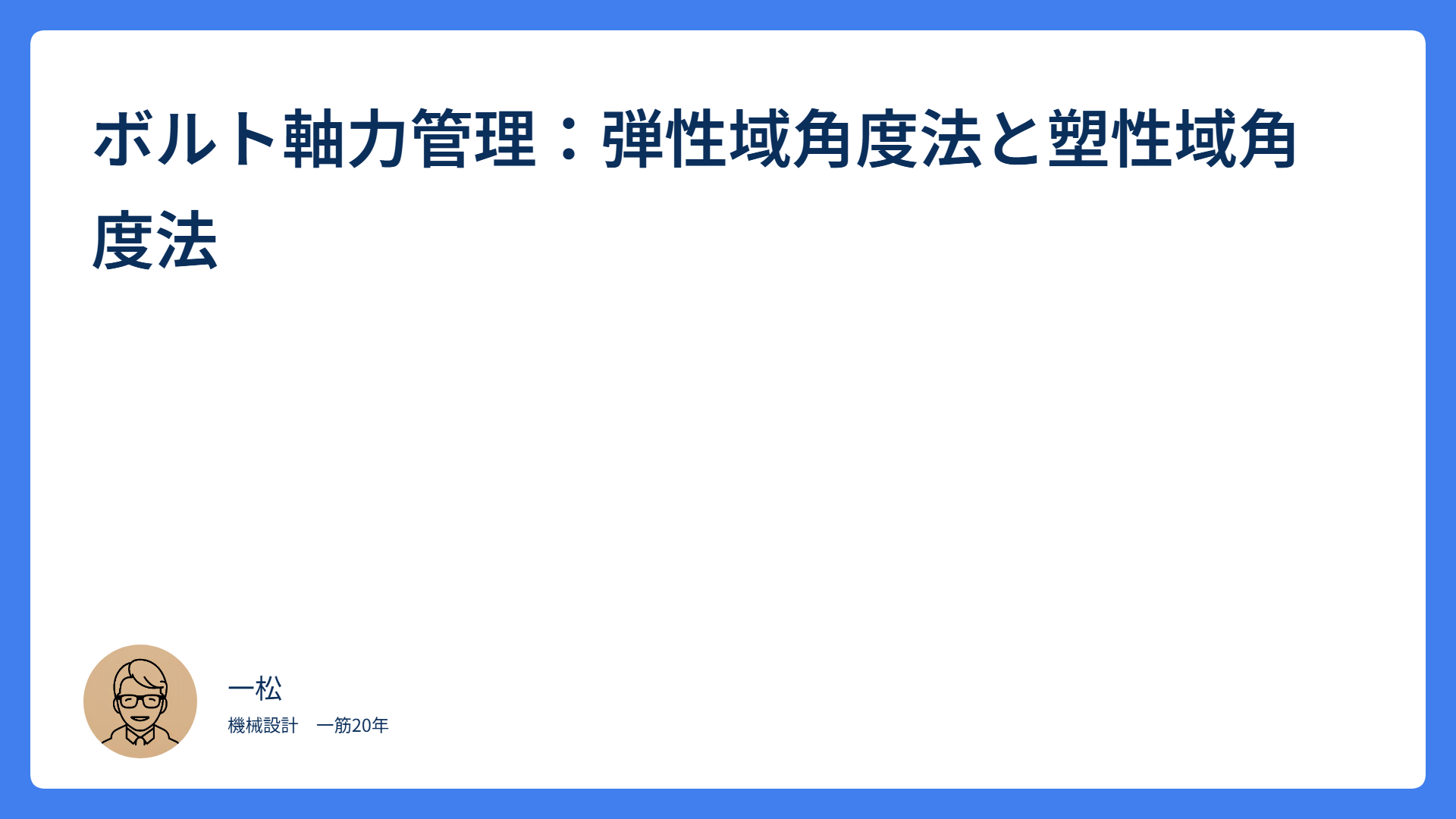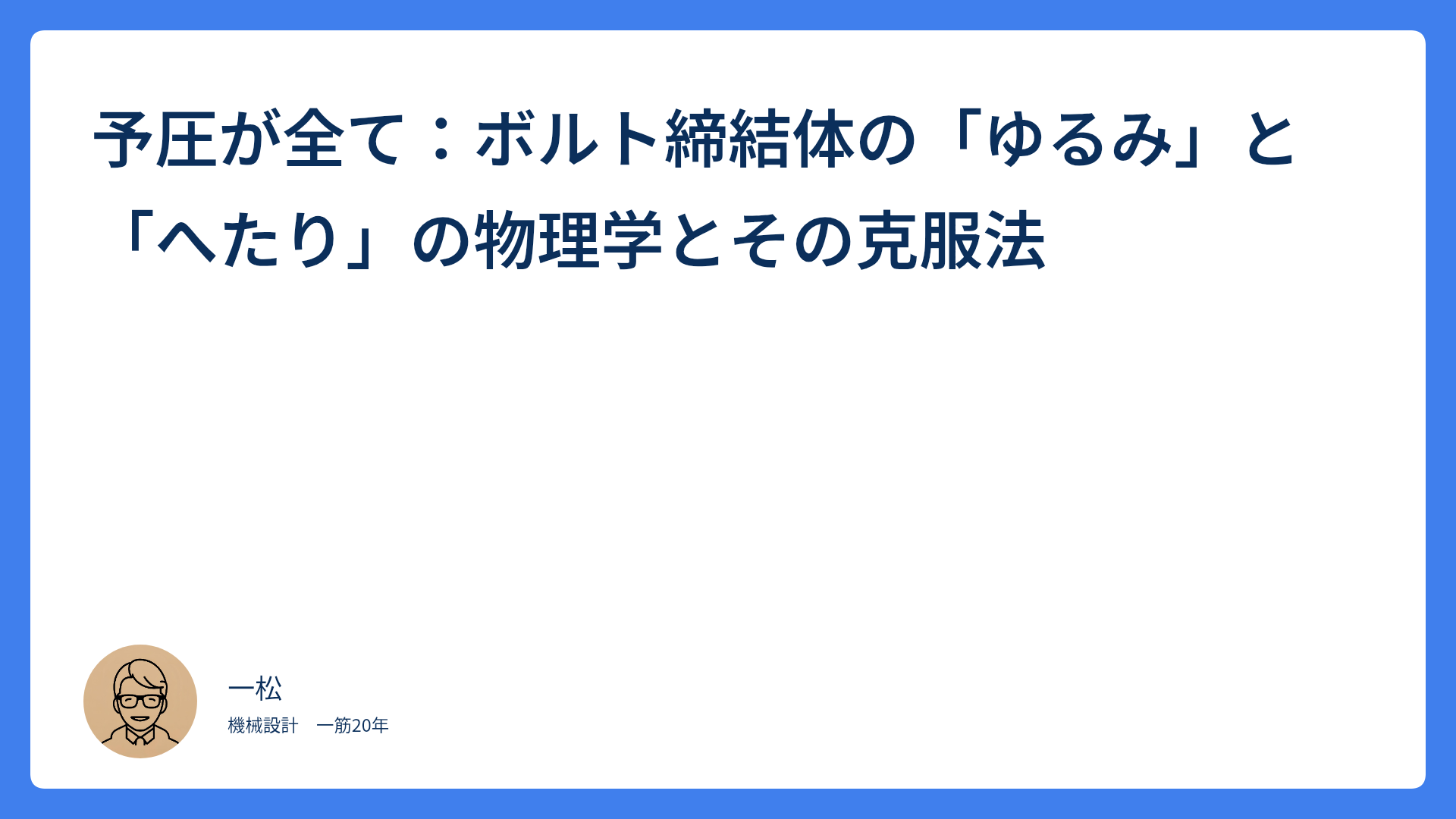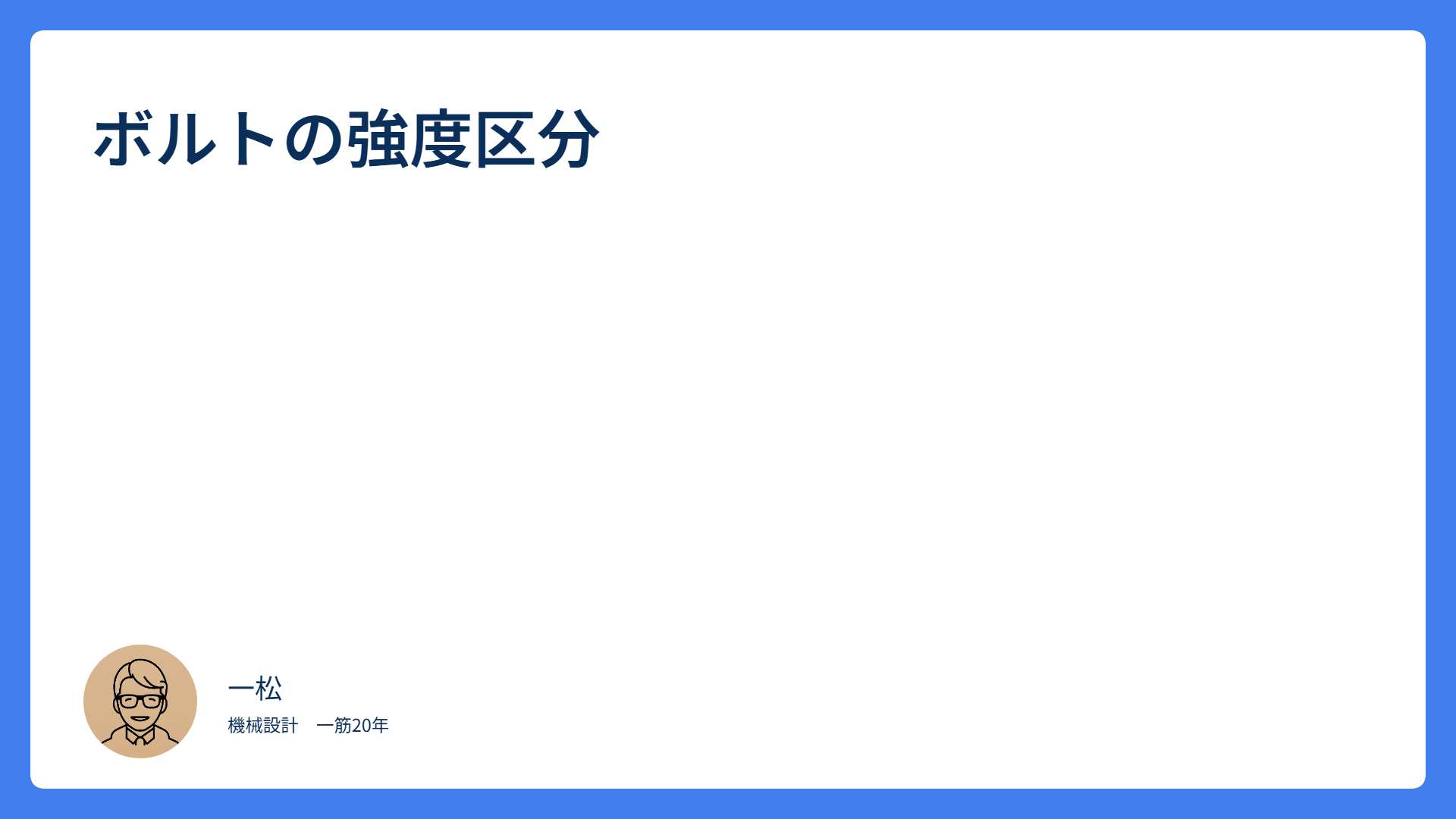なぜボルトは緩むのか?JIS規格に隠された「座面角」の秘密
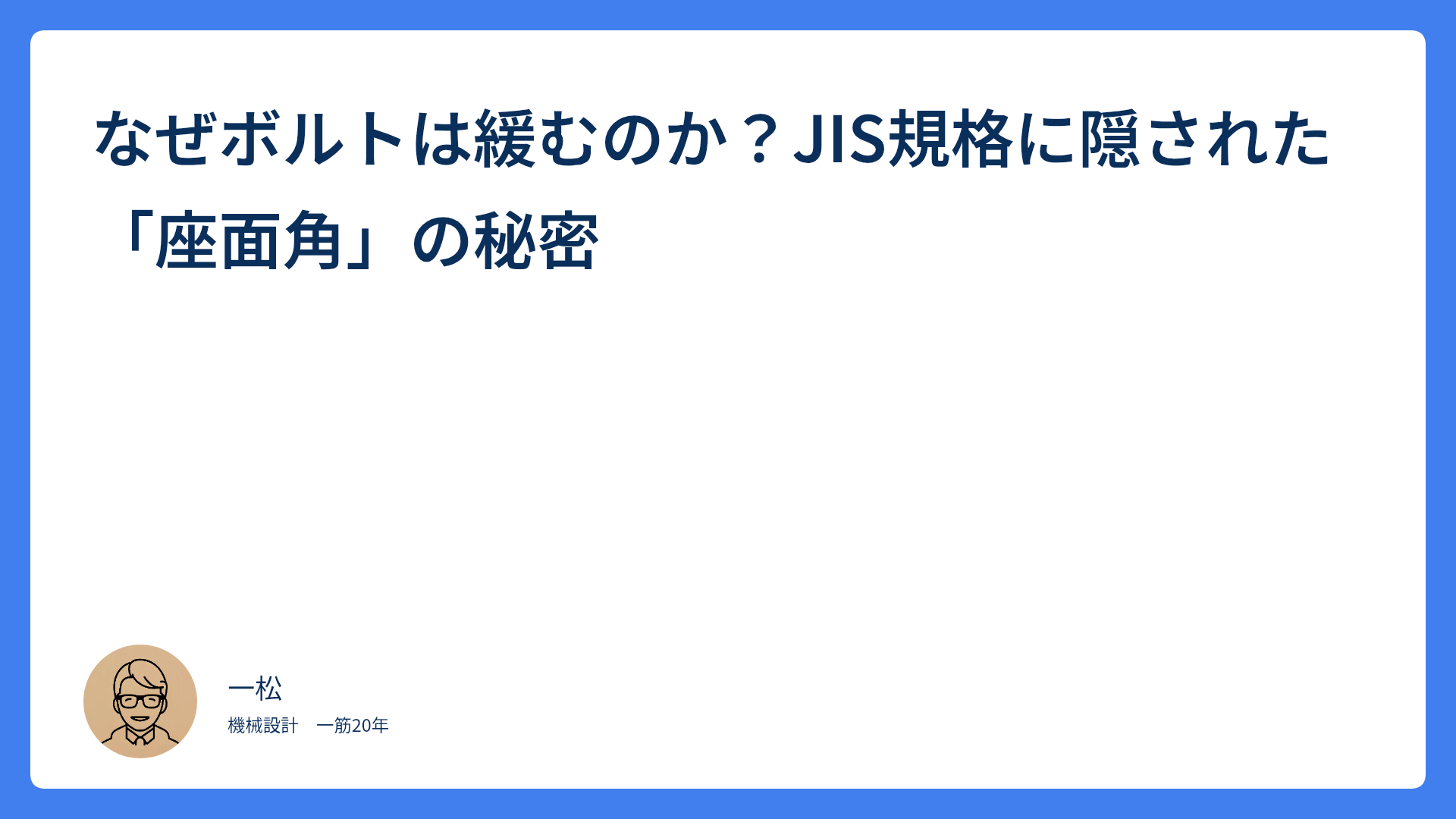
「規定トルクで締めたはずのフランジボルトが、なぜか緩んでしまう…」
「計算通りの軸力が出ていない気がする…」
その原因は、目には見えないボルトの「座面角」にあるかもしれません。特に、自動車や産業機械で多用される「フランジ付き六角ボルト」には、その信頼性を決定づける重要な角度の規定が存在します。
今回は、JIS B 1189「フランジ付き六角ボルト」の規格を基に、締結の成否を分ける座面角の科学に迫ります。
わずか1°の攻防!JISが定める「外アタリ」の保証
JIS B 1189では、フランジ付き六角ボルトの座面(相手材に接触する面)の角度φについて、0.75° ± 0.5° と明確に定められています。
これを計算すると、角度の範囲は 最小で0.25°、最大で1.25° となります。
ここで最も重要なのは、この角度が絶対にマイナスにならない、つまり座面の中央がへこんだ形状に設計されているという点です。
なぜなら、これにより座面の外周部から相手材に接触する「外アタリ」が確実に保証されるからです。
緩みの元凶「内アタリ」を防ぐ設計思想
もし仮に、座面角がマイナス(座面の中央が盛り上がった「バンザイ」状態)だったらどうなるでしょうか。
この場合、座面の中央部分だけが相手材に接触する「内アタリ」という最悪の状態を引き起こします。
内アタリは、締結の信頼性を著しく損なう2つの大きな問題を引き起こします。
1. てこの原理による「緩み」の発生
内アタリでは、接触点が中央の狭い範囲に限定されます。ここに力が加わると、その接触点を支点とした「てこの原理」が働き、ボルトが非常に緩みやすくなります。特に、振動、熱膨張による伸縮、繰り返し荷重といった外力が加わる過酷な環境では、このわずかな回転が積み重なり、致命的な緩みへと発展するため、座面角の管理はより一層重要になります。
2. 計算通りの締結力が得られない
ボルトの締結設計は、トルクレンチでかけた力が「ねじ面の摩擦」と「座面の摩擦」を経て、最終的にボルトを伸ばす力(軸力)に変換されることを前提に計算されています。
しかし、内アタリによって座面の接触面積が極端に小さくなると、
- 異常な面圧の発生: 狭い点に力が集中し、相手材を傷つけたり、座面が陥没したりする原因になります。
- 摩擦の不安定化: 接触状態が不安定なため、トルクが正しく軸力に変換されません。結果、トルクレンチの数値は正しくても、設計者が意itした締結力は全く得られていない、という事態に陥るのです。
これは他人事ではない?量産時に潜む罠
「試作品では全く問題が出なかったのに、量産に入った途端、原因不明の緩みやトルクダウンが頻発する…」
もし、このような事態に直面したら、量産でロットが変わったボルトの座面角を疑ってみてください。試作で使ったボルトは規格通りでも、量産ロットの品質にばらつきがあり、内アタリのボルトが混入している可能性は十分に考えられます。
また、この座面角の問題は、フランジボルトに限りません。特に、元々座面面積が小さいキャップボルト(ソケットヘッドボルト)やボタンボルトなどでは、内アタリの影響がよりシビアに現れるため、同様の注意が必要です。
まとめ:信頼性は細部に宿る
フランジ付き六角ボルトに規定された 0.25°~1.25° というわずかな座面角。これは、単なる製造誤差の許容範囲ではありません。
必ず「外アタリ」を実現させ、内アタリによる緩みと締結力不足を防ぐという、安全思想に基づいた極めて重要な設計値なのです。
ボルトを選定する際は、強度区分や材質だけでなく、こうしたJIS規格に準拠した適切な形状で作られているかを確認することが、機械や構造物の信頼性を確保する上で不可欠と言えるでしょう。